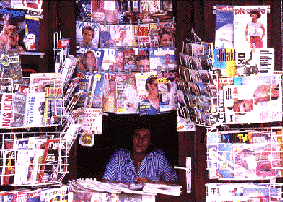|前へ|次へ|アドリア・アルペンの旅目次|

スロヴェニアとクロアチア
クロアチアとスロヴェニアは、その首都の間が150キロほどしか離れていないのに、確かに別の文化圏に属しているようである。歴史的にはクロアチアがハンガリー王国に属し、スロヴェニアがクライン地方というハプスブルクの直轄領であったことは紛れもない事実としても、それが人々の生活の端々にまで現れている。食事一つ取ってみても、サラミと干し肉が並べばもうこれはスイスか南ドイツである。スープは素麺のようなものを浮かしたブイヨンとかクラフトブリューエと呼ばれる日本でいうコンソメである。そしてシュヴァイネブラーテン。これがクロアチアとなるとダルマチアではイタリアの、ザグレブではバルカンやハンガリーの影響が大きく、ドブロブニクではオリーブ油をたっぷり使ったギリシャやビザンチン風の料理になってくる。
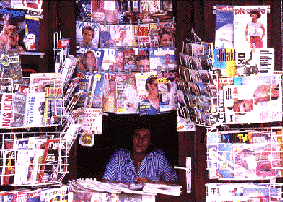 |
| リュブリャーナの売店 |
もう一つ驚いたのはTVの放送で、ザグレブではCNNやSKYが英語で四、六時中ニュースを流しているのに、ラシュコではどこをひねってもドイツとオーストリアのチャネルである。ラシュコの街はスロヴェニアというか、かっては旧ユーゴスラヴィア最大のビール工場を持っていて、今朝(14日)もドイツの友好都市の人々が、この元来ビール工場に附属していたホテルで、お土産を沢山貰って帰るところに出くわした。食堂でもドイツ語が溢れている。私としては何となくアットホームになるわけである。
登りつめた教会には鍵がかけられていたが、その少し手前の別荘に毎週末出かけてくる人に、自分の葡萄畠で作ったツビチェックを是非飲んで行け、と呼び止められテラスに案内された。ここでも視界は180度位には拡がっている。
先ず赤ワインを美味しい美味しいと飲むと、これはとっておきの自作のブランディだと、松の実と蜂蜜のブランディを次々に飲ませてくれた。まさに行きずりの通りがかりの人を捕らえて一杯一緒にやろうというホスピタリティは、戦後、日本人がなくした一番大きな忘れ物ではないだろうか。チヴェツコ氏と別荘の主人の間には共通の知人の話題が出て、話がはずんでいった。

|前へ|次へ|アドリア・アルペンの旅目次|